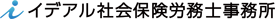コラム
コラム
労働時間の適正な把握について大きく3点にしぼっておさらい
目次
はじめに
2017年1月に労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインが策定され、その後、2019年4月に働き方改革関連法により長時間労働者に対する面接指導等が強化されました。
上記に係わる労働時間の適正な把握について、大きく3点にしぼっておさらいしていきます。
①労働時間の考え方
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。
例えば、下記のようなケースです。
・使用者の指示により業務終了後に掃除等をしたり、業務上命じられ制服等への着替えをする時間
・使用者の指示があったら即時に業務へ服する業務に従事することが求められている手待ち時間
・参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練の時間
②労働日ごとの始業・終業時間を確認し、適正に記録していく
【原則の時間管理】
・使用者が自ら現認する(使用者が自ら確認し記録をつけていく)
・タイムカード、ICカード、勤怠管理システム等の客観的な記録を用いて確認し、適正に記録
【例外としてやむを得ず自己申告制で行う場合は一定の要件あり】
・労働者、管理者に対して十分な説明を行う
・必要に応じて、自己申告した労働時間とPCのログで実態との乖離がないか確認する
・労働者からの適正な自己申告を阻害する措置を設けない
③管理監督者含むすべての労働者の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握
健康の観点から管理監督者含むすべての労働者の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握することが、2019年4月の改正により義務となりました。
消滅時効期間・書類の記録の保存期間など
2020年4月より未払い賃金の消滅時効期間が3年(原則5年当面の間3年)に延長され、あわせて、賃金台帳などの記録の保存期間も3年(原則5年当面の間3年)に延長されました。
まとめ
以上、労働時間の適正な把握についてのおさらいでした。
労働時間の適正な把握には、クラウドの勤怠管理システムによる把握がおすすめです。
導入していない事業者様は是非ご検討ください。
【参考】
厚生労働省:使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
厚生労働省:「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf
厚生労働省:未払賃金が請求できる期間などが延長されています
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
【関連サービス】
クラウドサービスの導入